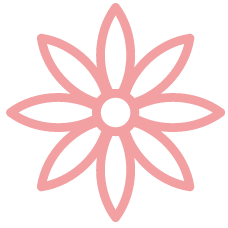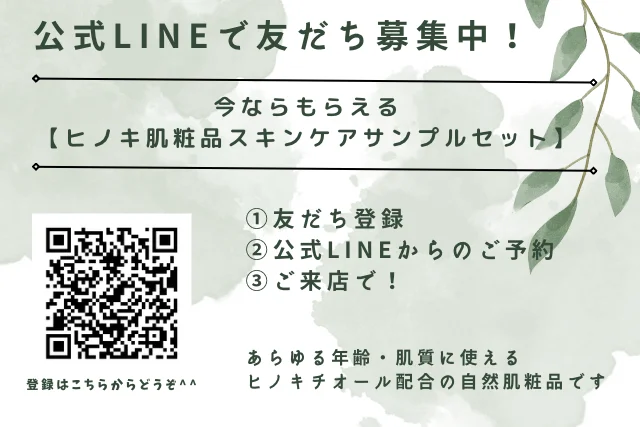冬が近づくと耳にするインフルエンザの話題。「今年は流行が早いらしい」なんて声も聞こえてきますね。
毎年のように流行をくり返すインフルエンザですが、予防の段階でも発症後のケアでも、漢方を取り入れた体調管理が役立つことがあります。漢方は「体質やそのときの状態に合わせて無理のない回復を支える」という考えかたを大切にしているのです。
ウイルスを敵とみなして直接戦うのではなく、身体がもつ自然な回復力を整えるのが重要だといわれています。
インフルエンザと身体の関係を知る

インフルエンザは「ウイルスによる感染症」といわれますが、漢方では身体の状態しだいで症状の出方が変わると考えます。疲れがたまっているときや身体が冷えているときなど、スキを見つけて外からの影響(外邪〈がいじゃ〉)が入り込むのです。
〈ウイルス=外邪〉に負けないための基本
外邪とは、体外から侵入してくる病気の原因となる要素(ウイルスや細菌など)です。
人間の身体には「衛気(えき)」という防御の力があり、身体の表面で外邪に抵抗しているのです。天然マスクのようなものですね。
衛気が十分に巡っていれば外邪を寄せつけません。衛気を保ち、身体を守る働きを支えるのが基本です。
身体のバランスが乱れると防御力が下がる
漢方の基本にあるのは、「気(き)・血(けつ)・水(すい)」の調和です。どれかが滞るとバランスが崩れ、巡りも鈍ります。
たとえば冷え性のひとは血の流れが悪く、ウイルスに対する反応が遅れやすい傾向があります。身体のリズムを保つことがなによりの予防なのです。
体質に合わないケアが逆効果になることも
「たくさん汗をかけば早く治る」と無理に厚着すると、体力を奪ってしまうことがあります。逆に、冷えを感じているのに身体を冷やすような飲食を続けると、治りが遅くなることも。
漢方では状態をていねいに見きわめ、いまの身体に合う方向へ整えていきます。
インフルエンザにかかりやすいひとの傾向

同じ生活をしていても体調を崩すひとがいる一方で、周囲が寝込んでも元気に過ごすひともいますね。日ごろの過ごしかたや体質の違いが、インフルエンザへのかかりやすさに影響しています。
冷えやすく汗をかきにくい
身体が冷えていると、ウイルスを外へ押し出す力が弱まります。下記の症状や傾向は、体温調節や免疫機能に影響を与える可能性があり、要注意です。
- 手足が冷たい
- 冷たい飲みものを好む
- 厚着が苦手
冷えは血の流れを滞らせ、免疫細胞の働きを鈍らせます。寒さに強いひとでも、夏の冷房や冷たい飲食が積み重なると、秋冬に不調を招きやすくなるのです。
疲れやすく睡眠不足が続いている
気(き)は身体のエネルギーそのもの。気が不足すると、防御の力も落ちてしまいます。忙しい毎日で休息を削っていると、衛気を立て直す時間がありません。ちょっとした疲れが積み重なると、感染症の波に巻き込まれやすくなります。
胃腸が弱く風邪をひきやすい
胃腸は栄養を吸収して気を生み出す中心的な臓です。食べものの消化が滞るとエネルギーも十分に補えないため、冷えやだるさが続き、感染を防ぐ力が弱まります。「食欲が出ない」「朝から身体が重い」と感じたら、すでにサインが出ているかもしれません。
胃腸の消化吸収についてはこちらをどうぞ!
脾の働きと体調管理のカギ【五臓六腑から健康を学ぼう】
インフルエンザを予防し回復を助ける漢方の考えかた

インフルエンザを防ぐうえで大切なのは全体の調和を整えること。免疫の働きを支えるうえでも重要です。漢方では今の状態を見極め、身体の巡りを整えていきます。予防・発症初期・回復期、それぞれの考えかたをご紹介します。
予防に役立つ考えかた
疲れがたまりやすく、季節の変わり目で体調を崩しやすいひとは、身体の土台を整えましょう。
漢方では、気を補ってエネルギーの巡りを支える考えかたがあります。代表的な例として、補中益気湯(ほちゅうえききとう)が知られています。「朝から身体が重い」「気力が出にくい」と感じるときは、疲れをためこまないよう、こまめに休息をはさんでください。
冷えや貧血傾向のある女性は、気と血(けつ)をともに補いましょう。体力が落ちていると感じるときは、気と血の両方をゆっくり補ってあげることが大切です。十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)が代表例として知られています。
どちらも、日々の疲れを積み上げないよう支えるものです。
発症初期のケア
ゾクゾクする悪寒・関節の痛み・熱っぽさなどを感じる発症初期には、身体のなかにこもった熱を外へ逃がして回復を助けましょう。
古くから知られる漢方薬に麻黄湯(まおうとう)があります。発汗をうながして、こもった熱を外へ逃がす目的で用いられてきました。「服用したら布団にくるまって汗をかく」→コレ、とても大事です!
ただし、体力が落ちていたり高齢の場合は、汗をかかせすぎると負担になるかもしれません。そのようなときには、冷えを和らげながら呼吸を整えるタイプの漢方薬が合う場合もあります。麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)などが知られています。
どちらの場合も、体力や症状に合わせて無理のない回復を目指しましょう。
回復期のサポート
熱が下がっても身体がだるく回復が進まないときには、柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)が用いられることがあります。気の巡りを整え身体の芯から回復を促していき、次の不調を繰り返さないためのケアにもつながります。
「元気が戻らない」と感じたら、状況に合うケアに切り替えていきましょう。
肩の力をすこ〜しゆるめて

インフルエンザの報告がポツポツ聞かれるようになりました。身体を整えることが、免疫の働きを支える土台になります。
冬の寒さは身体だけでなく、心にも影響しますよね。寒さで肩に力が入り、呼吸が浅くなっていませんか? 温かい飲みものでホッと一息ついてください。ゆっくり息を吐くだけでもリラックスを促し、巡りが少しずつ整っていきますよ。
漢方薬は、特別なときに使う病気の薬ではありません。日々の疲れや冷えを見直し、自分の力を取り戻すきっかけをくれる味方なんですね。インフルエンザ流行の知らせに不安を感じたら、身体をいたわる合図かもしれません。
毎日できる体調管理のコツを書いています。ぜひ参考にしてくださいね!
受験生の体調管理|漢方薬剤師が教える合格までの健康術
自分に合う漢方薬がわからないときや、体質に不安があるときはご相談ください。あなたに、いま必要なケアを一緒に見つけていきましょう。
空気がだんだん冷たくなっていきますね。心と身体が温まる日々を過ごせますように。