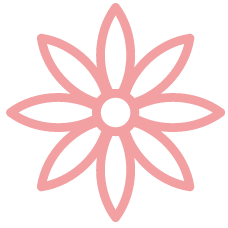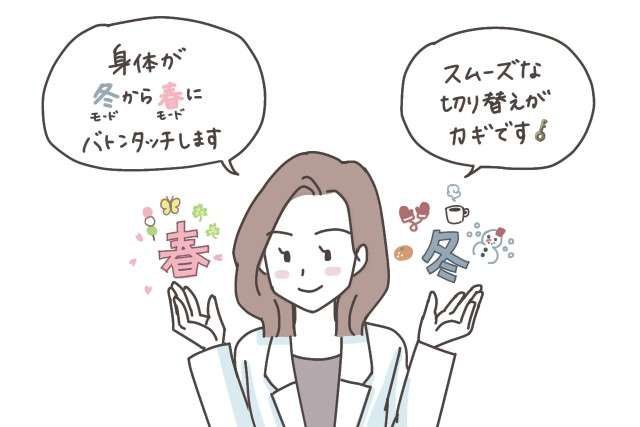季節の変わり目や台風が近づくと、頭痛やめまいに悩まされることはありませんか?
これは「天気痛」や「気象病」と呼ばれる症状です。科学的な証拠はまだ不十分なのですが、多くのひとにとって困難な現実問題ですよね。
感受性や心理的要因が大きく関わっているともいわれます。天気痛を感じるひとは自分に合う対処法を知っておくといいですね。
天気痛とは? 気象の変化が身体に与える影響と仕組み

気圧の変化や湿度の変動によって、頭痛・めまい・関節痛などの症状が現れる状態を天気痛と呼びます。
天気痛を感じないひとには理解しにくいのですが、実際に身体が気象変化に反応して起こる現象なのです。特に低気圧が近づくときや季節の変わり目に症状が悪化するのが特徴です。
天気痛が起こる主な原因
気圧変化による身体への影響
気圧が急激に低下すると、身体の内側と外側の圧力バランスが崩れます。頭蓋骨内には脳脊髄液(のうせきずいえき)という液体があります。この液体や内耳(ないじ:耳の奥)の圧力変化が、頭痛やめまいを引き起こすのです。
気圧が5hPa(ヘクトパスカル)以上急激に下がると、天気痛を感じる方の多くが症状を自覚するという研究結果があります。「急激に気圧が5hPa以上下がる」といわれても理解しにくいと思いますが、台風や低気圧が接近する際によくみられるものです。
一方で、気圧が上昇する際に頭痛を感じる方もいます。これも同様のメカニズムで、気圧の急激な変化に身体が追いつかないのです。上昇にしろ低下にしろ、気圧の変動には注意が必要です。
自律神経の乱れと血流の変化
気象変化は自律神経系にも影響を与え、頭痛やめまいを引き起こすことがあります。流れを簡単に説明すると以下のようになります。
低気圧が近づく
→交感神経が優位になる
→血管が収縮する
→反動として血管が拡張する
→脳内の三叉神経を刺激し痛み物質が放出される
→頭痛が生じる
身体の水分バランスと代謝の変調

湿度や気温の変化は、身体の水分バランスや代謝にも影響します。東洋医学では「気・血・水」のバランスが乱れることで、頭痛やめまいなどの症状が現れると考えます。
天気が悪い日にむくみやすくなるのも、水分バランスの乱れが関係しているのです。
気温上昇と頭痛の関係
春先や夏の初めごろなど、気温が急激に上昇する際にも頭痛を訴える方がいます。暑さによる体温調節機能の乱れが血管を拡張させ、頭痛を引き起こします。
また、気温上昇に伴う湿度の変化や大気中の汚染物質の増加も頭痛の一因となることがあります。
天気に左右されない身体づくりのための3つのアプローチ

自律神経を整える生活習慣を
規則正しい生活と適度な運動は、天気痛対策の基本です。天気のよい日に20分程度の有酸素運動をしましょう。自律神経のバランスが整い、天気痛への抵抗力が高まります。
十分な睡眠を確保すると、身体の回復力も向上しますよ。ストレスを軽減することも自律神経の安定に欠かせません。深呼吸やリラクゼーションを取り入れてみましょう。
耳のマッサージも効果的です。耳の周りには自律神経を調整するツボが集中しています。耳をマッサージすることで交感神経と副交感神経のバランスを整えられるんですね。
また、耳周辺の血流を改善するので、内耳の状態も整います。内耳は気圧の変化を感知するセンサー。血行がよくなると、内耳の過剰反応を抑えられますよ。
- 耳をつまむ: 親指と人差し指で耳の上部をつまみ、上・下・横にそれぞれ5秒ずつ引っ張る
- 回す: 耳を軽く横に引っ張りながら、後ろ方向にゆっくりと5回まわす
- 包む: 耳を包むように折り曲げて5秒間キープ
- 円を描く: 手のひらで耳全体を覆い、後ろ方向に円を描くようにゆっくりと5回まわす
※天気痛についてはこちらもどうぞ
気圧の変化と身体の不調
食事で内側から身体を整える

東洋医学では薬食同源という考え方があります。食べ物と薬は同じ源であり、適切な食材を摂取することで健康を維持し、病気を予防するという理念なんですね。
薬食同源を天気痛に応用すると、以下のような食材が効果的といえます。
- 大豆製品(豆腐・納豆など)
マグネシウムやビタミンB群が豊富で自律神経を整えるのに役立つ - ナッツ類(アーモンド・くるみなど)
マグネシウムやビタミンEが豊富。抗酸化作用があり、ストレスを軽減する - 海藻類(わかめ・ひじきなど)
ミネラルが豊富で体内の水分バランスを整えるのに役立つ - 根菜類(生姜・にんにくなど)
身体を温める作用があり血行を促進する - 果物(バナナなど)
エネルギー源として優れており血糖値を安定させる。天気の変化による体調不良を防ぐ - 香味野菜(玉ねぎ・しそなど)
気の巡りを良くしストレスを軽減する
温かい食事を中心に、規則正しく食べましょう。糖質をとりすぎると血糖値が急上昇し、自律神経を乱す原因となります。おやつはナッツや干し芋など、栄養豊富なものを適度に。
※必見! 甘味料の選びかた
砂糖はなぜマイルドドラッグと呼ばれるのか|本当は怖い砂糖依存症
体質から改善する
漢方薬を用いた体質改善は、天気痛がある方に対するアプローチのひとつです。身体を整えると自律神経のバランスが保たれ、気圧の変化に対する過剰な反応を抑えられるようになるんですね。
以下は天気痛の症状を和らげるためによく使われる漢方薬です。
- 五苓散(ごれいさん)
体内の水分バランスを整える代表的な漢方薬 - 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
血の不足を補い、水の巡りをよくする - 補中益気湯(ほちゅうえっきとう)・健脾散(けんぴさん)
脾虚(ひきょ|消化器系の状態)に対して用いられることがある漢方薬
※個々の体質や症状に応じた選薬は大切なプロセスです。必ず薬剤師に相談しましょう。
症状別・体質別の漢方アプローチ

天気痛は症状の現れ方や体質によって対策が異なります。主な症状パターン別の対応法をご紹介します。
ズキズキ型頭痛には
ズキズキとした痛みを感じる頭痛は、東洋医学では「肝陽上亢(かんようじょうこう)」タイプに分類されることが多いです。このタイプはストレスや疲労が蓄積している方に多く見られます。肝の機能が過剰に働き、頭痛を引き起こすのです。
日常生活に、深呼吸や軽いストレッチなどのリラックス法を取り入れましょう。ストレスを軽減し身体の緊張をほぐすことが大切です。
漢方薬は肝の働きを整えるものをおすすめしています。
重だるい頭痛には
頭が重く、だるさを感じる頭痛は「痰湿(たんしつ)」タイプです。痰湿は、消化器系の働きが弱まり、体内に余分な水分が溜まって、頭部に影響を及ぼすことがあります。湿度が高い時期や天候が不安定な時に悪化しやすいですね。
甘いものや脂っこいものを控え、消化を助ける食材を選びましょう。利尿作用のある食材(冬瓜やとうもろこしのひげ茶など)もおすすめです。
痰湿の方には、身体の水分代謝を改善する漢方薬が適しています。
ふらつきめまい型には
ふらつきやめまいを感じる場合は「気血両虚(きけつりょうきょ)」タイプの可能性があります。この体質は「気」と「血」が不足しており、エネルギーが足りないため、さまざまな不調を感じるかもしれません。ストレス・過労・栄養不足・睡眠不足などが原因で、脳への血流が不足しているのです。
栄養バランスの取れた食事を心がけ、ストレス管理や十分な休息を取ることが症状の緩和に役立ちます。
漢方薬は、気血を補い全身のエネルギーを高めるものが適しています。
天気痛と上手に付きあうには?

天気痛は完全に消えるものではないので、上手に付きあっていきましょう。当店のお客さまからも天気痛のご相談が増えてきました。適切なケアを続けることで症状が軽減し、天気に左右されにくい身体づくりに成功している方もたくさんいらっしゃいますよ。
大切なのは症状が出てから対処するのではなく、日頃から予防的に身体を整えておくこと。天気のよい日こそ、身体のメンテナンスに最適です。
また、ご自身の症状の特徴やパターンを知っておきましょう。天気痛ダイアリーをつけて、どんな気象条件で症状が出やすいかを記録してみると、傾向がみえてくると思います。
日本人の約7割が何らかの天気痛を自覚しているという調査報告もあります。特に女性の割合が高い傾向にあります。ひとりで抱え込まず、専門家に相談したり、同じ悩みを持つ方と情報交換したりすることも、精神的な負担を軽減するのに役立ちますよ。
当店ではお一人おひとりに合った東洋医学的アプローチをご提案します。気になる症状がありましたら、お気軽にご相談くださいね。