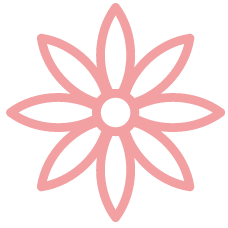春の訪れとともに新たな一歩を踏み出すシーズン。希望に胸を膨らませる反面、「なんとなく気分がすぐれない」「疲れやすい」という声も聞こえてきます。
東洋医学では、春の不調は「肝(かん)」と深い関わりがあると考えます。今回は新生活のスタートに向けて、肝を整えることでストレスを軽減し、春を元気に過ごすためのヒントをお届けしましょう。
春の不調の原因は「肝」にあり!五行説から読み解く季節の変化
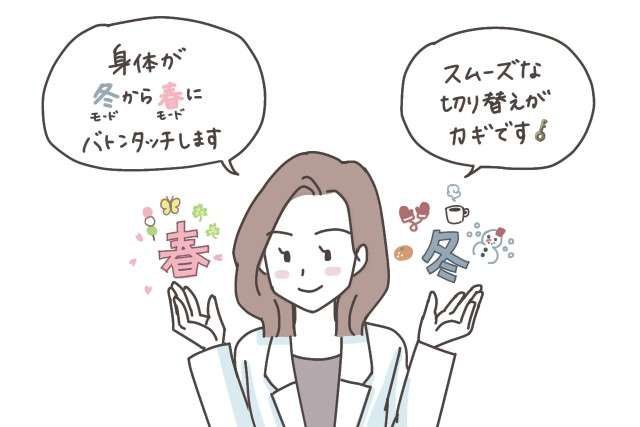
東洋医学の「五行説」では、春は「木」の季節とされ、五臓の「肝」と結びついています。
春になると自然界では草木が芽吹き、成長期を迎えます。わたしたちの身体も同様に、冬の間に蓄えたエネルギーを使って活動的になろうとするのです。
五行説における「肝」と「春」の特別な関係
五行説では各季節と臓が対応しており、春は肝の季節です。肝は冬の「腎(じん)」から受け継いだエネルギーを使って、身体全体の活動を促す役割を担っています。肝と腎は密接に関連しているんですね。
桜前線が北上するにつれ、わたしたちの身体も冬モードから春モードへと切り替わります。切り替えがスムーズにいかないと、さまざまな不調として表れるのです。
肝が乱れるとどんな症状が現れる?

肝の機能が低下すると、次のような症状が現れやすくなります。
- 眼精疲労やドライアイ(肝は「目」と関連)
- イライラや感情の起伏(肝は「怒り」の感情と関連)
- めまいや頭痛(気血の巡りの乱れ)
- 筋肉のこわばりやけいれん(肝は筋肉の動きをコントロール)
- 生理不順(女性の場合)
春の不調が肝の機能低下と関連していることは、多くの文献でも言及されています。
春に特有の「気滞(きたい)」という状態
東洋医学では、エネルギーの流れが滞った状態を「気滞(きたい)」と呼びます。春は特に気滞が起こりやすい季節なのです。気の流れが滞ると、胸が苦しくなったり、ため息が増えたり、気分の浮き沈みが激しくなったりします。
新生活のスタートは期待と不安が入り混じるもの。不安定な心理状態が気滞を引き起こし、肝の機能に影響を与えることもあるんですね。
新生活のストレスが肝を疲れさせる3つの理由

環境の変化は身体にも心にも大きな影響を与えます。特に新生活のスタートは、知らずしらずのうちに肝に負担をかけていることがあります。
リズムの変化による自律神経の乱れ
新しい生活環境では、起床・就寝時間や食事の時間など、生活リズムが大きく変わることがありますね。生活リズムの変化が約2週間続くと自律神経のバランスが崩れ、肝機能にも影響を与えるといわれています。
新生活のスタート時には、起床後すぐに太陽の光を浴びる、規則正しい食事を心がけるなど、新しいリズムを早く身体に定着させることが大切です。
人間関係の変化によるストレスの蓄積

新しい環境での人間関係構築は、大きなストレス要因です。初対面の人との会話は、慣れた相手との会話に比べてエネルギーを多く消費しますよね。
このエネルギー消費が肝の疏泄作用(そせつさよう)に負担をかけ、疲労感やイライラの原因となることがあるのです。
※疏泄作用=新陳代謝と考えてください。詳しくはこちらを
肝を整える|あなたの不調は春のせい!【五臓六腑から健康を学ぼう】
デジタル機器の使いすぎによる肝への影響
新生活に伴い、新しいシステムやデジタル機器を長時間使用することが増える方もいらっしゃるでしょう。ブルーライトは睡眠ホルモンの分泌を抑制し、肝の回復を妨げることがあります。
目は肝と直結している器官です。スマートフォンやパソコンの使いすぎは目の疲れだけでなく、肝の機能低下にもつながるのです。1時間に10分程度は目を休める時間を作りましょう。
肝を労わって元気に新生活を送るための方法

肝の機能を高め、春の不調を和らげるためのポイントをご紹介します。あなたの日常生活に取り入れやすい方法から始めてみましょう。
旬の食材で肝を元気に! 春の食養生法
東洋医学では「春は苦味」といわれています。春の苦味野菜が肝の働きを助けるんですね。
- 菜の花
- ふきのとう
- うど
- たけのこ
春野菜には、冬の間に溜まった老廃物を排出する働きがあります。1日に小鉢1皿程度を目安に食べましょう。
色で選ぶなら、緑色の食材(青菜、ブロッコリー、アスパラガスなど)が肝のエネルギーを補うのに効果的です。
その他、春野菜ではありませんがクコの実もおすすめです。スマホやPCの使いすぎによる眼精疲労や視力低下を防ぐといわれています。甘くておいしいですよ。
肝をリフレッシュする呼吸法とストレッチ

深い呼吸は気の流れを促進し、リラックス効果があります。これが肝の機能を高めるのに役立つんですね。仕事や勉強の合間などに、呼吸法を試してみましょう。
- 楽な姿勢で座り、目を閉じます
- 鼻から4秒かけてゆっくり息を吸います
- 2秒間息を止めます
- 口から6秒かけて息を吐き出します
- これを10回繰り返します
また、肩回りや脇腹を伸ばすストレッチも効果的です。特に「木のポーズ」と呼ばれるヨガのポーズは、肝の気の流れを良くするといわれています。体幹を強化し姿勢を改善する効果があるポーズで、肝の機能をサポートするんですよ。
休息の質を高めて肝の回復力を上げる
肝は睡眠中に最も活発に回復するため、質の良い睡眠が重要です。特に午後11時から午前3時までは、肝が血液を浄化し解毒するという大切な作業をしています。
睡眠の質を高めるために、就寝前にはスマートフォンやパソコンの使用を控え、ぬるめのお湯で入浴するなど、リラックスできる習慣を取り入れましょう。
休日には「なにもしない時間」を意識的に作ることも大切です。ただボーッとする時間も肝の回復に役立つんですよ。予定を詰め込みすぎず、緩やかな気持ちを大切にしましょう。
春はゆっくりスタートでだいじょうぶ!

春の訪れとともに新しいスタートを切る方は、期待と不安が入り混じっていることでしょう。少しでも身体の不調を感じたら「肝」からのサインかもしれませんよ。
自然界の木々が少しずつ芽吹くように、わたしたちも少しずつ新しい環境になじんでいけばいいんです。頑張ることも必要ですが、無理しすぎず、ゆっくり新しい生活に適応していくくらいでちょうどいいかもしれません。
自分の「いい加減」を知るといいですね。
新年度がスタート!ゆっくり始めてもいいんじゃない?
「肝を大切にする=自分自身を大切にする」ことです。春の不調に悩まされたら「ゆっくりでいいんだ」と思い出してください。
当店もカウンセリング&体質に合わせた漢方薬で、新生活を応援します。新しい季節、新しい環境での出会いや発見が、あなたの人生をより豊かなものにしますように。