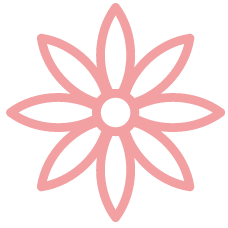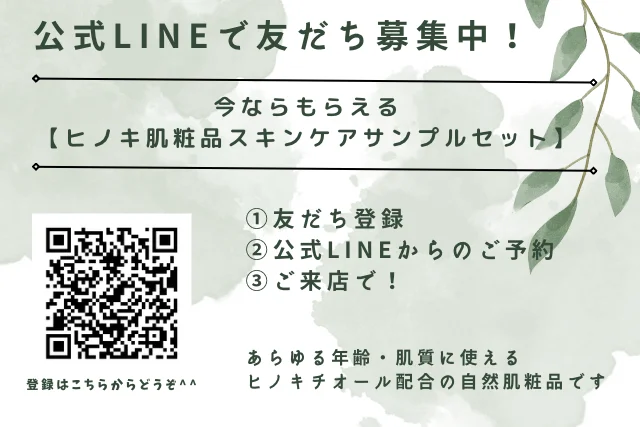あなたは朝、スッキリ目覚めていますか?
疲れているから早く眠りたいのに眠れない……なんてことはありませんか?
原因はいくつか考えられます。生活を振り返ってみましょう。
夜は身体のメンテナンス時間です
現代社会は目まぐるしく、24時間稼働状態です。
本来、人間の身体には“夜眠くなる”メカニズムが備わっているのですが、どこかで調子が狂うと身体にも影響がでてくるんですね。
あなたの生活はいかがでしょうか。

睡眠にも深い関係があるセロトニン
まずはセロトニンのお話から。
セロトニンは“幸せホルモン”として有名ですが、睡眠にも関係があるんですよ。
セロトニンは朝から分泌が始まります。
そして起床から14〜16時間後に、今度はメラトニンというホルモンが作られます。
メラトニンは質のよい眠りに必要なのですが、セロトニンの分泌が少ないとメラトニンの量も少なくなってしまいます。
身体の疲労と脳の疲労
1日中PCと向き合っていたり、物事を深く考えたりすると、脳が疲れてしまいます。早く眠りたいのに目が冴えてしまった経験はありませんか?
身体の疲れと脳の疲れがアンバランスだと、質のよい睡眠は訪れません。
疲れがとれないのはなぜ?
睡眠に欠かせないメラトニンと成長ホルモンの不足
メラトニンには成長ホルモンの分泌を助ける働きもあります。成長ホルモンは子どもだけでなく、成人にも必要なのです。
メラトニン不足=成長ホルモン不足。
原因は、夜型生活・ストレス・日光を浴びていないなど、現代を現しています。

成長ホルモンが不足すると健康に影響が出てきます。
- 疲労の蓄積
- 活性酸素の蓄積(老化の元)
- 自律神経が乱れる(イライラの元)
- 肌荒れ
- 痩せにくくなる
身体と脳が休んでいない
人間は長時間眠らずにいると、脳細胞が破壊されてしまいます。現在ギネスブックでは危険を考慮し「眠らない」関係の記録は受け付けていないそうです。
睡眠は心と身体のメンテナンスのためにあります。眠っているあいだにひとの身体がしているのは
- 体温調節
- ホルモンの分泌
- 記憶や感情の整理
- 免疫機能の調整
脳をじゅうぶんに休ませてあげる必要があるんですね。
睡眠のシステム
レム睡眠とノンレム睡眠という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
レム睡眠は浅い眠り、ノンレム睡眠は深い眠りです。ひとは眠っているあいだにレム睡眠とノンレム睡眠を繰り返しているのです。
眠りに落ちた直後は急激に深い眠りになり、脳を集中的に休ませています。
あなたは夢を覚えていますか?
もし覚えているなら、眠りが浅いともいえますよ。
質のよい睡眠をとるためにできること
睡眠は、私たちが思う以上に大切です。
ぐっすり眠り、スッキリ目覚めるためにできることはなんでしょうか。

食事
セロトニンは朝日を浴びることで増やせますが、食事でも増やせるんですよ。
セロトニンを増やすのに必要不可欠なのはトリプトファンという必須アミノ酸です。
トリプトファンは体内で作れないので、食事やサプリメントから摂取します。
トリプトファンが多く含まれている食材は、乳製品・大豆製品・バナナなど。朝食でとりやすそうですね。
運動
デスクワークのひとは身体を動かす意識を持ちましょう。通勤手段で歩く過程を入れてみるなど、少し変えるだけでも違います。
トリプトファンをセロトニンとして活動させるためにも運動は効果的です。ストレスも入眠の妨げになるので、身体を動かして発散してくださいね。
入浴
寝る時間から逆算して1〜2時間前に入浴しましょう。10時就寝なら遅くとも9時までに入浴する計算です。
お湯の温度は38〜40度が最適。寒い時期は特にぬるく感じると思いますが、ゆっくりと30分くらい浸かるのが理想です。
理由はリラックス効果を高めるため。副交感神経を優位にし、入眠しやすくするのが目的です。熱いお風呂に入ると逆に交感神経が活発になってしまいますよ。
身体の深部から温まると、お風呂から上がったあと体温が下がると共に眠気がやってきます。身体が冷えていると入眠しにくいのです。
起床時の工夫
朝は起きる時間を一定にしましょう。朝日を浴びてセロトニンの分泌を促します。
遮光カーテンをお使いなら少し開けておき、窓から朝日が入るようにすると自然な目覚めに近づけますよ。
メラトニンの分泌が高まるのは、起床から14〜16時間後です。6時に起きるなら、22時頃には寝る準備に入りましょう。
安眠できる環境づくり
寝室の環境もチェックしましょう。
寝具の肌ざわりを気に入ったものにしたり、好きな香りを探してみてください。
アロマではラベンダーやイランイランなどがリラックスする香りといわれますね。
睡眠障害について
睡眠の質が悪いと疲れもとれません。
いろいろ試しても眠れないなら、別の理由が隠れているかもしれませんね。
交感神経が優位のまま→リラックスできない→眠れない
負の連鎖になっているのです。
身体が休息を求めているのに眠れないのはなぜでしょうか。
身体的もしくは心理的な理由、環境や薬剤の影響など、不眠には必ず理由があるはずです。解決できない場合は専門医への相談も考えてみましょう。
当店ではあなたの状態をじっくりお聞きしますので「話すだけでも心が軽くなる」と多くのお客さまに喜ばれています。心と身体はつながっているという漢方の考え方が表れているなぁと思うんですよね。
基本的な生活習慣を見直し、質のよい睡眠を目指しましょう。うまくいかなくても、ひとりで悩まないのが大切です。
あなたのこと聞かせてくださいね。