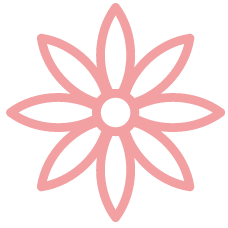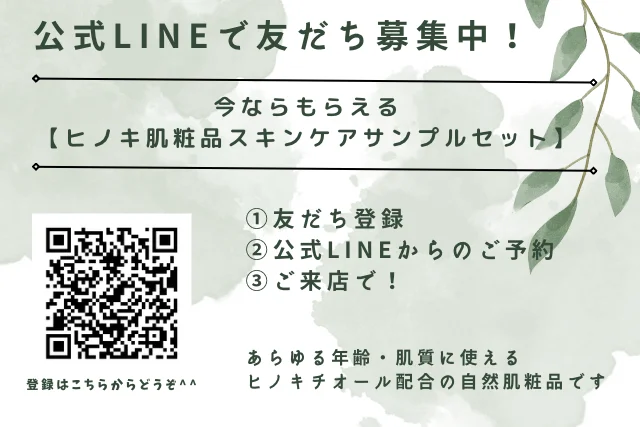寒くなってきましたが、夜間に何度も尿意で目が覚めていませんか? 夜間頻尿には、冷えや生活リズムの乱れが関係している場合があります。
東洋医学では、夜間頻尿は腎(じん)の働きが深く影響すると考えられています。腎は生命エネルギーを蓄える臓であり、寒さや加齢の影響を受けやすい場所なのです。夜間のトイレは、身体が発している小さなサインかもしれません。
夜間頻尿は腎の働きが影響している

腎は身体の“根”を支える臓
東洋医学でいう腎は「腎臓」という器官だけを指すのではなく、より広範な概念を含んでいます。成長・発育・生殖・老化など、生命活動の根を支える重要なはたらきを担っているのです。
腎の力が弱まると、尿をためたり、排出を整える力が低下しやすくなります。夜間頻尿は、腎の働きがゆるやかになってきた兆しといえるでしょう。
腎の弱りがもたらす夜の不調
腎が冷えると尿をためる力が弱まり、夜間に何度も目が覚めることがあります。眠りが分断されると深い睡眠がとれず、腎が本来行う回復の働きが十分に発揮されません。朝のだるさや疲労感が残りやすく、昼間の集中力にも影響が出てきます。
年齢や性別による違い
50代以降になると腎の機能が徐々に低下し、体内の水分やエネルギーを調整する力が弱まっていきます。男性では前立腺の変化、女性ではホルモン低下が影響することもありますが、年齢のせいと決めつけず、腎をいたわる生活を意識しましょう。
秋冬に夜間頻尿が増える主な原因

冷えが腎を弱らせる
秋から冬にかけては、冷気が下半身から腎へと伝わりやすくなります。足元やお腹を冷やすと腎の動きが鈍り、尿をためにくくなるのです。靴下や腹巻きなどで下半身を温めるだけでも変わってきます。温めることは腎を支え、身体のめぐりを整える養生なのです。
水分の摂りかたが偏っている
水分の摂りかたが偏っていると、夜間の尿量が増えやすくなります。夕食時や入浴後に多くの水分をとる習慣はありませんか? カフェインを含む飲み物は利尿作用があるため、夕方以降は控えめにしましょう。「のどが渇いたら一口ずつ」を意識すると、水分の摂りすぎを防げます。
生活リズムの乱れと腎の関係
夜更かしや不規則な睡眠は、腎のエネルギーを消耗させます。腎は夜間に回復する臓です。ストレスが続くと腎の精(せい)が減り、冷えや倦怠感としてあらわれてくるんですね。
冬はエネルギーを蓄える時期ですので、早めの就寝や静かな時間を大切にすると、腎もゆるやかに整っていきます。
快適な眠りを守るための工夫

身体を芯から温める習慣
冷えを感じる季節は、内側からの温めを意識しましょう。足湯や湯たんぽで下半身を温めると血流が巡り、眠りも深まりやすくなります。ストレッチで軽く身体を動かすのも緊張がほぐれるのでおすすめ。「温める時間」は、腎をいたわる時間でもあります。
夕方以降の水分リズム
水分を控えすぎると血流が滞り、疲労が抜けにくくなります。夕方以降は量を減らし、就寝2時間前までに摂取を終えるのが理想です。昼間はこまめに水分摂取して、夜は控えめにしましょう。このリズムが腎を楽にします。
漢方的な整えかた
食養生では、腎を支える黒い食材を取り入れましょう。
- 黒ごま:老化防止や疲労回復に
- くるみ:冷え性のひとに
- 山芋:疲れやすいひとに
体質に応じて、次のような漢方が選ばれることもあります。
- 八味地黄丸(はちみじおうがん):加齢による冷えや夜間頻尿に用いられる
- 牛車腎気丸(ごしゃじんきがん):足腰の冷えやむくみをともなうタイプに
- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん):疲れやすく、冷えとめまいを感じやすい女性に
- 十全大補湯(じゅうぜんたいほとう):体力の回復を支えたいときに選ばれることがある
同じ夜間頻尿でも、冷え・疲労・むくみ・ストレスなど、原因はひとにより異なります。体質を考慮しながら選薬するのが大切なので、薬剤師に相談しましょう。自分に合う整えかたを見つけていく過程が、腎を守る養生になります。
眠りは腎を守る時間です

夜の眠りは、腎が静かにエネルギーを蓄える時間。夜間に目が覚めやすいときは、身体が休まっていないのかもしれません。冷えを防ぎ、水分摂取を工夫してみてください。季節のリズムに合わせて暮らすのが、自然に寄り添ういちばんの養生なんですね。
漢方薬は、冷えやストレスなど体質に合わせて、夜の排尿リズムを整えるお手伝いをします。心地よい眠りが得られるよう、腎を整えていきましょう。ぜひご相談くださいね。