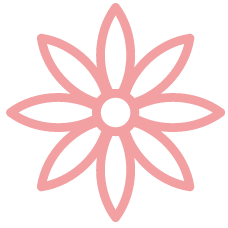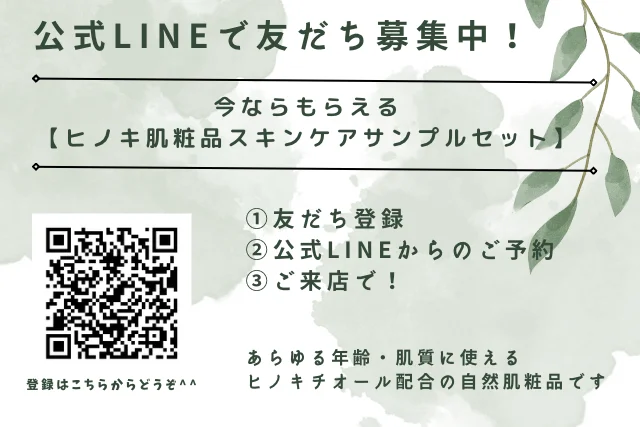塩分制限は腎機能を保護し、体内の水分バランスを維持するために非常に重要です。しかし味気ない食事では満足感が得られず、気持ちまで沈んでしまいますね。
「おいしく食べたい」という気持ちや食事を楽しむことは、心身の健康にとって大切な要素。食事はただの栄養摂取ではなく、満足感や生きる希望にもつながるのです。
本記事では、漢方の食養生(しょくようじょう)の知恵を交えながら、楽しめる食事の工夫をお伝えします。ご家族の食事を作る方もぜひ参考にしてください。
腎臓病における塩分制限の意味とは

塩分が腎臓に与える負担のメカニズム
塩分を摂りすぎると体内に水分がたまりやすくなり、血液の量や圧が上がります。すると、腎臓のなかにある糸球体(しきゅうたい)というフィルターが休む間もなく働き続け、やがて疲れてしまうのです。
日本人の1日の平均塩分摂取量は約9〜10gとされ、目標である6g未満を超えるひとが多いのです。醤油や味噌など、塩分を多く含む調味料を使う日本の食文化では、塩分摂取量が高くなりがちなんですね。
手軽に食べられるカップめんにも塩分が多く含まれています。
【カップめんに含まれる塩分の例】
- カップめんA:7.9g
- カップめんB:5.5g
- カップ焼きそばA:5.7g
知らないうちに腎臓へ負担をかけていることもあるので、意識して減らすのが大切です。
漢方から見た塩分と腎(じん)の関係
漢方では「腎」は生命エネルギーを蓄える臓とされます。
塩味(えんみ)は少量であれば腎を養う働きを助けますが、摂りすぎると反対に「腎気(じんき)」を弱めてしまうと考えられています。過剰な塩分摂取は腎臓に悪影響を及ぼしてしまうのです。
「しょっぱい=悪い」ではなく、適度な塩味のバランスが腎を守るカギとなります。
制限の目的と期待できる効果
塩分制限の目的は塩を減らすこと自体ではなく、腎臓を守るために血圧やむくみを整えることにあります。塩分制限は慢性腎臓病(CKD)の進行予防を目的とした、食餌療法のひとつとして推奨されています。
食事を見直した結果、身体が軽く感じられたり朝のむくみが減ったりと、変化を感じるひとは多くいるのです。「がまん」ではなく「自分をいたわるケア」として向き合うのが、長く続けるコツです。
塩分制限が続かないのはなぜ?

味に物足りなさを感じてしまう心理的要因
長年の食習慣で「濃い味=おいしい」と感じる味覚に慣れていると、薄味に違和感を覚えるかもしれません。「おいしく食べたい」という自然な気持ちが、制限への抵抗に変わってしまうのです。食の満足感が減ると、心も満たされなくなってしまいます。
家族との食事で孤立感を抱いてしまう環境的要因
家族と同じ食卓についていても自分だけ食べるものが違うと、なんとなく寂しさを感じてしまいますね。「家族に気をつかわせたくない」という思いと「健康を守りたい」という気持ち。複雑な思いで心が揺れやすく、ストレスになることもあるのです。
外食や市販品への依存による実践の困難
仕事や外出が多く外食やお惣菜に頼る方は、塩分量を把握しにくいでしょう。栄養成分表示を見ても判断が難しく、なにを選べばよいのか分からない方が多いのです。食の自由が減るとストレスも増し、続ける気力が保ちにくくなってしまいます。
塩分制限でも満足できる漢方の知恵を活かした食事法

天然の旨味成分を活用した調味テクニック
塩分を減らしても満足できる味づくりには「うま味」を味方につけることが大切です。昆布やかつお節、干ししいたけには天然のうま味成分が豊富に含まれています。
だしを上手に利用すると、少ない塩でも味に奥行きが出ます。グルタミン酸とイノシン酸を組み合わせると相乗効果が生まれ、より豊かな味わいが得られますよ。トマト・玉ねぎ・しじみなどもうま味が多く、スープや煮物のコクを深めてくれます。
- 昆布・トマト・玉ねぎ:グルタミン酸
- かつお節・しじみ:イノシン酸
- 干ししいたけ:グアニル酸
しょうゆや塩を減らす代わりにごま油や香味油を少量、または減塩しょうゆスプレーをひと吹きするだけで香りが立ち、満足感が高まります。
五味のバランスを整える食材選びのコツ
漢方では、食べ物の味を「酸(さん)・苦(く)・甘(かん)・辛(しん)・鹹(かん=しおからい)」の五味で考えます。塩分を控えるときは酸味や苦味を上手に使うのがおすすめです。レモンや酢を少し加えると味が締まり、塩を減らしてもおいしく感じますね。春菊やゴーヤのほろ苦さも、味のアクセントになります。
白・赤・緑・黒・黄の五色(ごしき)を意識すると彩りが豊かになり、それぞれの食材が持つ栄養素をバランスよく摂取できます。視覚的にも満足感を得られ、心身によい影響を与えるのです。
腎臓を補う食材でメニューの工夫を

漢方では、黒い食材や水分バランスを整える食材を意識するとよいとされています。
- 黒豆・黒ごま:香ばしさがあり塩分が少なくてもおいしさを感じやすい
- きのこ類:うま味が豊富でスープや炒め物の味を支える
- 山芋:「気」を補うといわれ、なめらかな食感が料理全体をやさしくまとめる
- 香味:しょうが・しそ・ゆず・レモンなどを添えると香りが立ち、味に立体感が生まれる
香りやうま味を工夫すれば、家族と同じメニューでもそれぞれの味加減に調整できますね。
外食や市販品で塩分を控えるちょっとしたコツ
塩分制限を続けるうえで、外食やお惣菜を完全に避けるのは難しいですよね。「全部を完璧に減らす」よりも、少しの工夫で「取りすぎないようにする」のが継続の秘訣です。
たとえば
- 汁物は半分ほど残す
- タレやソースは“かけずにつける”
- 漬物や加工食品の量を控える
- 「減塩」「だしのうま味」などの表示を参考にする
コンビニやスーパーでは「主菜+副菜のセット」よりも、単品を組み合わせて自分で調整するのがおすすめ。お惣菜を買う場合は野菜・きのこ・豆製品をプラスすると、味のバランスが整うので満足感があがります。
外食を控えるのが難しければ「どう選ぶか」「どう味わうか」に意識を向けてみましょう。塩分制限を“続けられる習慣”に変える第一歩です。
食事制限を前向きに取り組むために

塩分制限はがまんの生活ではなく、自分を守るおまもりです。味覚や食習慣は少しずつ変わっていくもの。焦らず、自分のペースで整えていきましょう。あまり堅苦しく考えず、おいしく食べる工夫を楽しめるといいですね。
モチベーションを維持するには、具体的な目標をもち、計画を立てるのが有効です。食事の記録や定期的な健康チェックを続けましょう。
最初は食材や調味料選びにも迷うと思いますが、やりながら慣れていくのがベストです。視点が変わるといつものスーパーでも「こんなものが売っていたのか」と新たな発見があるんですよね。無理のない範囲で好きな食材を取り入れるなど、食事を楽しむ気持ちを大切にしていきましょう。
漢方薬は、体質や生活習慣に合わせて、バランスを整えるサポートとして取り入れられます。腎臓の働きが気になる方も、無理のない方法を一緒に考えていきましょう。どうぞお気軽にご相談ください。