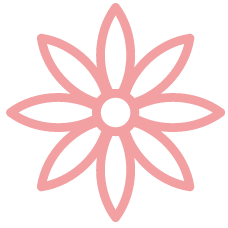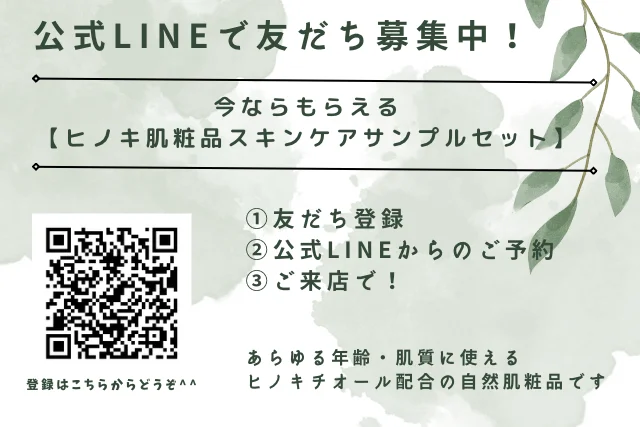起立性調節障害は、自律神経の働きがうまく調整できず、立ち上がったときのめまいやだるさ、頭痛などが出やすい症状です。今回は、起立性調節障害と向き合った小中学生のお話です。
朝起きると頭が痛くなる、塾がある日は胃が痛くなる、身体がだるい……。彼らにはつらい日々が続いていました。生活を工夫してもなかなか変化が見られず、ご家族も心配されていたそうです。
起立性調節障害の症状が出始めたきっかけや、家庭での対応、漢方薬局でのケア事例をまとめました。新学期を前に、同じような症状に悩むお子さんやご家族の参考になれば幸いです。
症例:小中学生の姉弟が向き合った起立性調節障害

ご紹介するのは、中学1年生の姉と小学3年生の弟のごきょうだいです。お姉さんが中学校に入ってから体調に変化が出はじめ、弟さんも長く頭痛を訴えていたため来店されました。
お姉さんのケース
塾通いが始まった頃から、塾がある日の入浴後に必ず胃が痛くなるという状態が続きました。お母さんは食事の時間や内容を工夫。スープや消化のよいものを中心にしたり、塾前に夕食を取らせたりしましたが、症状は改善しませんでした。
詳しくお話を伺うと、背景が浮かび上がってきます。
- 塾や学校生活でのプレッシャー
- 急な生活環境の変化
- ストレスによる自律神経の乱れ
体質と症状に合わせた漢方薬をお選びし、生活面でのアドバイスをしました。
服用から2週間後のご報告では「胃の痛みがだいぶ減った」と感じられたとのこと。さらに2週間後には「痛みが気にならなくなった」とお話くださいました。
弟さんのケース

弟さんは以前から、日常のさまざまな場面で頭痛を訴えていました。
- 朝起きたとき
- 車に乗ったとき
- 遊んで帰ってきたあと
元気そうに見えるのですが、繊細で疲れやすい性格のため睡眠で疲れが取れないこともあったようです。「怠け」と誤解されがちですが、放置すると不登校につながることもあります。
弟さんにもお姉さんと同じ漢方薬をお選びし、睡眠の質を高めて自律神経のバランスを整えるようサポートしました。
2週間後には「頭痛の頻度が減ってきた」と感じられ、さらに2週間後には「朝の頭痛が週2回程度まで減った」とご報告いただきました。
ご姉弟には同じ漢方薬を選薬しました。それぞれの体質や症状にぴったり合ったため、比較的早い段階で体調の変化を感じられたケースです。
起立性調節障害の症状と起こる原因
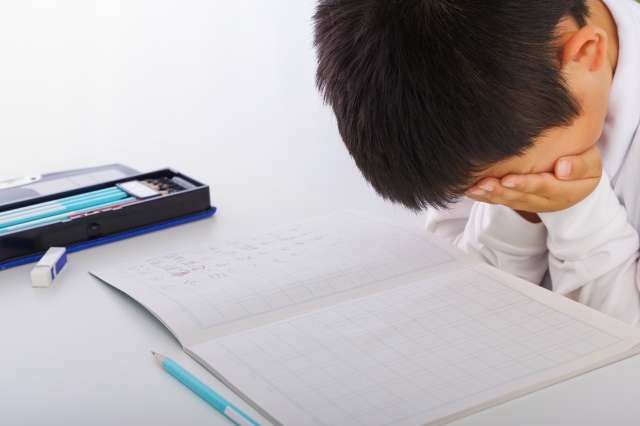
主な症状
起立性調節障害は身体にさまざまな不調が現れます。個人差はありますが、次のような症状が多くみられます。
朝起きられない・だるい
朝になると身体が重く、なかなか布団から出られません。支度や登校に時間がかかり、家族も本人も焦ったりイライラしてしまいがちですが、意志の問題ではありません。
頭痛・吐き気・胃痛
学校や塾、習い事の前後に頭痛や胃の不快感を訴えることがあります。症状が出るタイミングや強さは個人差があり、朝だけとは限りません。
周囲には元気そうに見えるため「怠けている」と誤解されやすく、本人は孤独感や不安を感じやすいのです。
気分の落ち込みや集中力の低下
体調の不安定さからぼんやりしたり、授業や宿題に集中できないこともあります。思うように学習が進まず、さらにストレスや疲れを感じやすくなります。
症状が現れる主な原因
思春期の身体や生活環境の変化によって自律神経のバランスが乱れ、症状が出やすくなります。主な要因は次の通りです。
自律神経の乱れ
自律神経は心拍や血圧、体温調整などをコントロールしています。急激な身体の変化や心理的ストレスによりバランスが崩れると、立ち上がったときのめまいやだるさ、頭痛などの症状が現れます。
精神的なプレッシャーやストレス
学校や塾、習い事での緊張や不安が続くと、身体が常に緊張状態に置かれ、自律神経が乱れやすくなります。胃痛・頭痛・胸の苦しさなどの症状として現れることも。
生活リズムや習慣の乱れ
夜型の生活や睡眠不足、運動不足は症状に影響します。寝ても疲れが取れず、日中のだるさや立位での気分不良が出やすくなります。
思春期に多い理由と発症しやすい子どもの特徴

思春期は身長や体型が急激に変化する時期で、身体の調整機能に負担がかかるため症状が出やすいのです。特に次の特徴を持つ子どもに起こりやすいとされています。
- やせ型の子ども
- 夜型生活や睡眠不足が続く子ども
- 学業や塾などのストレスがある子ども
- 運動不足で体力がつきにくい子ども
これらの特徴が必ず症状に直結するわけではありませんが、複数当てはまる場合は注意しましょう。保護者や学校の理解・サポートが、症状の負担を和らげる大きな力になります。
日常を取り戻すための生活と漢方薬のサポート

起立性調節障害に向き合うなかで子どもやご家族が望むのは
「普通に朝起きて学校に行けるようになりたい」
「体調を気にせず過ごしたい」
という日常の安定ですね。症状のサポートには、生活習慣の工夫が必要です。
規則正しい生活リズムを整える
朝起きやすい身体にするためには、睡眠リズムの安定が重要です。夜型生活や不規則な就寝は自律神経の乱れにつながりやすく、症状を悪化させる原因となります。
就寝・起床の時間を一定にすること、寝る前のスマホやテレビを控えることなど、小さな工夫が体調の安定につながります。
適度な運動と体力づくり
運動不足は疲れやすさや体調不良の一因です。軽い運動やストレッチを取り入れ、血流や自律神経の働きを整えましょう。激しい運動で無理する必要はなく、毎日少しずつ身体を動かすのがポイントです。
漢方薬によるサポート
症状や体質に合わせた漢方薬で、身体の調整機能を助けるサポートができます。お姉さんと弟さんのケースでは、体調の変化を比較的早く感じていただけました。漢方薬は生活習慣の改善と組み合わせると相乗効果を生み出しやすいのです。
家族や学校との連携

症状は見た目に表れにくく「怠けているのでは」と誤解されやすいため、家族や学校の理解と協力が支えになります。
朝は無理に起こそうとせず、体調の変化を受け止めながら生活を整えましょう。朝食の時間を工夫したり、登校前に軽く身体をほぐす習慣もいいですね。
学校との連携は重要です。担任や保健室の先生、スクールカウンセラーと情報を共有しておくと、子どもは安心して学校生活を送れます。授業の遅れや休憩の工夫など、個別のサポートも取り入れやすくなるのです。
- 無理に起こさない
- 担任・保健室・スクールカウンセラーとの情報共有
- 授業や休憩など学校での配慮
家庭と学校が協力し、子どもが支えられている実感を持つことが、生活の安定と体調のサポートにつながります。
お子さんが安心できる環境づくりを

起立性調節障害に向き合うお子さんやご家族の願いは、とてもシンプルです。
「普通に朝起きて、学校に行きたい」
日常を取り戻すためには、生活習慣の見直しと、必要に応じたサポートが重要です。
起立性調節障害で悩むお子さんやご家族にお伝えしたいのは「あなたはひとりではない」ということ。周囲の理解を得られず孤独を感じることがあるかもしれませんが、日々の小さな工夫や支えにより、少しずつ安心できる毎日が送れるようになってきます。
日々、お子さんの体調の変化を受け止めながら、生活リズムや食事の工夫を続けてください。学校側と情報を共有し、安心して学校生活を送れるようフォローしましょう。
漢方薬は体質や症状に合わせて選ぶことで、自律神経のバランスを整えるサポートになります。生活の工夫と組み合わせると、より日常が安定しやすくなりますよ。焦らず、少しずつ取り入れていきましょう。
思春期の子どもは変化の大きな時期で、体調の揺れもあります。保護者も学校も子ども自身も「無理をせず、支え合いながら少しずつ前に進む」ことを心がけてほしいと思います。子どものペースを大切に、周りと支え合いながら見守ってくださいね。
起立性調節障害のご相談を承ります。下記からご予約いただければしっかりと時間の確保ができます。どうぞご利用くださいませ。