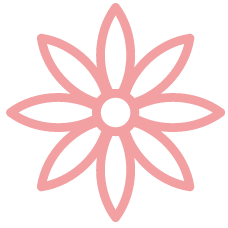ひと前で話すとき、自分の名前を言うとき、電話をかけるとき。言葉が出てこないつらさを抱えていませんか。
吃音(きつおん)は決して珍しいことではありません。全人口の約1%、つまり100人に1人が経験している症状です。学校での発表、職場での会議、日常的な会話まで、コミュニケーションのさまざまな場面で困難を感じている方が多くいらっしゃいます。
今回は吃音の基本的な知識からさまざまなアプローチ方法まで、薬剤師の視点でお伝えします。ひとりで悩まないでくださいね。
吃音とは言葉のリズムが乱れる発話の特徴

音の繰り返しや引き伸ばしが起こるメカニズム
吃音は「どもり」とも呼ばれ、話すときに言葉がスムーズに出てこない状態を指します。
- 音の繰り返し(連発):「あ、あ、あのね」のように同じ音を繰り返す
- 音の引き伸ばし(伸発):「あーーーのね」のように言葉の一部を引き伸ばす
- 言葉が詰まる(難発):「......あのね」のように言葉が出るまでに間があく
吃音は、脳の言語処理システムにおける連携の問題によって生じると考えられています。「話したいことを考える部分」と「実際に口や舌を動かす部分」の連携がうまくいかないのです。
緊張やストレスが加わると、言語処理システムの連携がさらに乱れやすくなってしまいます。
2歳から5歳頃に現れる発達性吃音の特徴

多くの場合、吃音は2歳から5歳の幼児期に始まります。言葉を覚え始めた子どもが、頭のなかにある豊富な言葉を口から出そうとするとき、まだ発達途中の発話機能が追いつかないために起こるんですね。
幼児期の吃音は「発達性吃音」と呼ばれ、約75%の子どもは成長とともに自然に改善されます。しかし、残りの25%の子どもは成人まで症状が続くことがあるのです。早期の適切な対応が、将来的な改善につながる可能性を高めます。
男性に3〜4倍多く見られる統計データ
吃音は男性に多く見られる特徴があり、女性の3〜4倍の発症率です。幼児期では男女差がそれほど大きくありませんが、成長とともに男性の割合が高くなる傾向があるのです。
遺伝的要因も関係しており、家族に吃音のひとがいると発症リスクが高くなります。ただし遺伝だけが原因ではなく、環境要因と複雑に絡み合って発症することが多いのです。
吃音の悩みが生まれる主な原因

遺伝的要因と脳の言語処理システムの影響
吃音は遺伝的要因が関係していると考えられています。特定の遺伝子の変異が、脳の言語処理や運動制御に影響を与えるのです。
脳科学の研究により、言語処理を担う脳の部位の活動パターンが、吃音のあるひととないひとで異なることがわかってきました。左脳の言語野と右脳の運動野の連携がうまくいかず、発話の困難さにつながっていると考えられています。吃音は単なる発声の問題ではなく、脳の機能に関連した複雑な障害なのです。
心理的ストレスと緊張が症状を悪化させる仕組み

吃音は心理的な状態に大きく左右されます。緊張や不安が高まると筋肉が硬くなり、呼吸が浅くなって、発話がより困難になってしまうのです。
「また話せなくなったらどうしよう」という予期不安が、実際に話しづらさを引き起こす悪循環に陥るんですね。リラックスしている家族との会話では症状が軽くなり、ひと前での発表では症状が重くなるという経験をする方が多いのも、心理的要因の影響を物語っています。
周囲の反応や社会的プレッシャーが与える影響
周囲からの「落ち着いて話して」「ゆっくり話して」といった言葉かけがかえってプレッシャーとなり、症状を悪化させる場合があります。本人は一生懸命話そうとしているのに、周囲の反応によって自信を失ってしまうのです。
コミュニケーションが重視される現代社会では、吃音のあるひとが感じる社会的プレッシャーは以前より大きくなっているでしょう。就職活動や昇進の場面で、話すことへの不安が人生の選択に影響を与えることもあるのです。
自然な会話を取り戻すためのアプローチ

言語療法と発声練習で基本的な話し方を整える
言語聴覚士による言語療法は、吃音改善の基本的な働きかけです。具体的には正しい呼吸法・発声法・発話のリズムなどの訓練をし、スムーズな会話につなげていきます。吃音のあるひとが自信を持って話すための基盤を築くのです。
- 流暢性形成法:ゆっくり話すことから始めて、段階的に自然な速度での発話を目指す
- 吃音軽減法:吃音が起こったときの対処法を学び、症状に対する不安を軽減していく
個人の状況に応じ、適切に組み合わせた訓練が行われます。
心理療法で話すことへの不安を和らげる
認知行動療法では、話すことに対する考え方や行動パターンを見直していきます。「完璧に話さなければならない」という思い込みを変えて「伝わればよい」という考え方に転換し、心の負担を軽くしていきます。
グループ療法では、同じ悩みを持つひとたちと経験を分かち合い、孤独感を軽減していきます。話すことへの恐怖心を和らげ、自信を取り戻すサポートが受けられます。
臨床心理士・公認心理師・言語聴覚士などの専門家が一人ひとりの状況に応じて適切な心理療法を提供し、吃音に関連する心理的な問題を解決する手助けをします。
栄養療法という新しい可能性

近年、吃音に対する栄養療法の研究が進んでいます。特定の栄養素が脳の神経伝達物質の働きに影響を与え、発話機能の改善に寄与する可能性があると考えられているのです。
当店でも、バイオリンクを継続的に摂取している男の子のお客さまがいます。ご家族からは「以前より元気に過ごしているように見える」というお声をいただきました。
ただし、栄養療法はまだ研究段階にあり、すべての方に効果があるとはいえません。環境や家庭のサポートも、発話への不安に影響を与える重要な要因なのです。個人の身体状況や栄養状態を考慮し、専門家の意見を参考にしましょう。他の療法と組み合わせて取り入れると、よりよい結果が期待できる場合があります。
周囲の理解とサポートが支える安心感

吃音で悩むひとの生活の質を向上させるためには、家族や友人、職場の同僚など周囲のひとたちの理解とサポートが欠かせません。適切な接し方を継続していくと、当事者が安心して話せる環境が作れるでしょう。
〈話を聞くときに心がけたいこと〉
相手の目を見て最後まで話を聞きます。途中で代わりに言葉を言ったり「ゆっくり話して」「落ち着いて」などのアドバイスは控えましょう。時間がかかっても、相手のペースに合わせて待つのが大切です。
〈学校や職場でできる配慮〉
発表の順番を事前に伝える、代替手段(筆記やジェスチャー)を認める、プレッシャーのかからない環境作りなどがあります。子どもの場合はクラスメイトへの正しい理解を促し、いじめや孤立を防ぎたいですね。
安心して話せる環境を作りましょう

吃音は一朝一夕で改善するものではありませんが、支えてくれるひとや方法があります。周囲の力を借りて小さなことから始めてみましょう。お子さんであれば周囲の大人が安心感を与えることで精神的な安らぎが得られ、症状が薄らいでいく可能性もあるのです。
話すことの困難さは人間の価値を決めるものではありません。持っている才能や人間性は話し方に関係ありませんので、吃音のために素晴らしい資質を潰してしまわないよう願っています。ひとりで悩まず、専門家や家族、友人に相談してみてくださいね。
当店ではお客さま一人ひとりの状況に寄り添いながら、身体の内側から健康をサポートしています。吃音でお悩みの方には栄養面でのアドバイスや、リラックス効果のある漢方薬の選薬も行っています。ご相談の予約は下記からどうぞ。