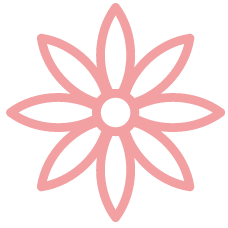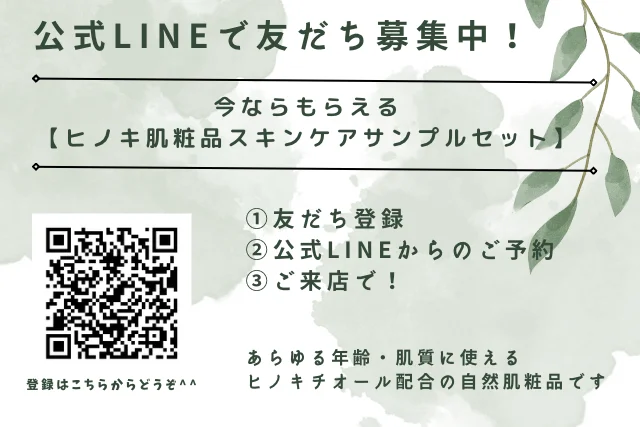ふきのとう・うど・タラの芽など、春野菜や山菜には苦味がありますよね。
中医学でいう「肝(かん)」は、血をため精神を安定させる働きがありますが、春は身体も心も不安定になりがちなので、肝がフル稼働するんです。
「春の皿には苦味を盛れ」といわれるのは、春の苦味野菜を食べて肝を助けてあげようという意味なのです。

体調のゆらぎに春の苦味野菜を
旬の食べ物は安くて美味しいだけじゃないんです。
人間も自然のなかで生かされてるんだなぁと思います。
春野菜はなぜ苦い?
春野菜の苦味はポリフェノールやアルカロイドなどの成分からきています。
一説によりますと、虫たちに食べられないよう香りや苦味を出しているとか。
春野菜はその苦味成分で自分たちを守っているんですね。
ひとはなぜ苦味野菜を食べたくなるの?
春になると自然に動きたくなりますよね。
これからの活動に向け、心身を整えたくて苦味野菜が食べたくなるんですって。
ちゃんと身体が求めているんですね。
春野菜の苦味の効果
▶︎新陳代謝を促進
冬は寒さを乗り切るため、身体が栄養分を溜め込みます。
春野菜の苦味は身体に刺激を与え、冬に蓄えてしまった余分な脂肪や老廃物を排出してくれるんです。
▶︎春野菜の栄養価
栄養価には傾向があり、多くの春野菜に下記のような成分が含まれています。
- カリウム…体内の塩分排出・むくみ解消
- βカロテン…抗酸化作用・免疫力UP
- ビタミンC…美肌・老化防止
- 葉酸…代謝促進・心疾患リスク低下・胎児の発育サポート
身体のサビを取り除き、健康でキレイになるために取り入れたいですね。

身近な春野菜の特徴と注意点
身体によいといってもやはり食べ過ぎはダメ!
スーパーで手に入りやすい菜の花とたけのこの特徴と注意点をお伝えします。
菜の花
菜の花には、殺菌作用があるイソチオシアネートなど数種類の苦味成分が入っています。
そのほかβカロテン・ビタミン類・葉酸・カリウム・鉄分などが豊富です。
茹ですぎると柔らかくなりすぎ、栄養分も流れ出てしまいます。
短時間で調理しましょう。
おひたしやからし和えがおいしいですが、油との相性がよいので炒めものもおすすめです。
たけのこ
たけのこのアクやえぐみの正体はシュウ酸とホモゲンチジン酸という成分。
疲労回復や自律神経を整えてくれます。
ただし、シュウ酸は結石の原因にもなりますので食べ過ぎに注意してください。
シュウ酸はカルシウムと一緒にとると、体内で結石化するのを防ぎます。
カルシウムを含むワカメとともに食す「若竹煮」は理にかなっていますね。
ほかにもカリウム・食物繊維・チロシンなどを含み、老廃物を排出します。
チロシンは、たけのこを茹でたときに付いている白いもの。
脳を活性化させるアミノ酸なので取らずに召し上がれ!
まとめ
春の苦味野菜にはうど・セリ・タラの芽・ふきのとうなど、今回ご紹介した以外にもたくさんあります。
ぜひ試してみてくださいね!
春になると苦味野菜がでてきて、私たちはそれを食べたくなります。
それにはちゃんと春らしい理由があるんですね。
自然の摂理を感じます。
漢方薬も自然のものからできており、副作用はありません。
なんだか調子がおかしい。
病名がつきにくい症状があればご相談ください。
一緒に体質改善していきましょう。